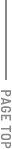風営法 京都の用途地域は大丈夫?
風営法に該当するお店を申請や届出して許可や受理されるには
いろんな法律や条例、規則等々の要件をクリアする必要があります。
ここでは、まず最初にクリアすべき要件の一つである用途地域について解説します。
お店を契約して手付金を払った後で、風営法の申請した際に
京都府の警察署から「この場所では許可が出せません」「この場所では受理できません」
となったら、かなり悲しい結果になってしまいますので、お店を契約する前に
お店の用途地域はどうなんだと確認してもらえる参考になれば幸いです。
京都で風営法のお店が出せる用途地域
大阪で風営法のお店が出せる用途地域でもお伝えしましたが、
都市計画法では13種類の用途に分けてそれぞれ、商業地域・住宅地域とか、工場地域に区分けされています。
次に建物を建築する際には、建築基準法が登場します。
先ほどの13種類の地域で建築基準法は建築できる建物を制限しているので、住宅地域に大きな工場とかは
立っていない訳です。
そこで京都で風営法のお店で出店できる用途地域ですが
・商業地域
・近隣商業地域
・準工業地域 ・工場地域・工場専用地域
になるのですが、工場地域は結局工場が多いわけでして、そこでお店を出すのはなかなか
のチャレンジャーと言えるのではないでしょうか。
結局、風営法のお店が出せる用途地域としては、商業地域か近隣商業地域になるのでしょう。
お店を契約した後に用途地域が商業地域や近隣商業地域でなかった場合
お店を契約して契約書も交わしたあとに、調べてみると商業地域、近隣商業地域で無かった
場合は困ってしまいますが、
ただ例外も京都府の場合ありまして
条例で「第1種住居地域、第2種住居地域及び準住居地域のうち、国道又は府道の側端から25メートル以内の地域」
「第1種住居地域、第2種住居地域及び準住居地域のうち鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第2条第2項に規定する鉄道に係る停車場(列車を停止し、旅客又は貨物を取り扱うため設けられた場所で転轍器の設備を有するものをいう。)の周囲50メートル以内の地域」はいいですよとなっています。
風営法で京都府の用途地域の例外
お店のある場所が、第一種住居地域、第二種住居地域及び準住居地域で「国道・府道」の道沿いにあって
道路から概ね25m以内ならばお店は出せますよとなっています。

あと同様に第一種住居地域、第二種住居地域及び準住居地域でお店のある場所が
駅(列車を停止し、旅客又は貨物を取り扱うため設けられた場所で転轍器の設備を有するものをいう)
から概ね50m以内の区域にあればお店をだせますよとなってます。
恐らく誰もが転轍器の設備?になりますね。
いわゆる他のレールに切り変えるポイントになります。

それでも調べた結果、最終的には、第一種住居地域、第二種住居地域及び準住居地域で
お店が決められた道路の近くや駅舎が近くに無い場合は、
許可は受けられず届出も受理されないことになります。
この道路とか駅とかはかなり細かくややこしいので、お店のある管轄警察署か
風営法専門の行政書士に確認されることをお薦めします。
まとめ
今回は京都府の風営法の用途地域についてお伝えしました。
京都府では10の各都市計画区域において用途地域がありまして、各市町が都市計画決定をしています。
従ってお店のある市役所に「用途地域を確認したい」と直接電話して確認するのが、
一番早いと思います。
ただ用途地域は問題なくとも、接待をする予定のスナック、
キャバクラやホストのお店の近くに保全対象施設があったらアウトになります。
保全対象施設のコラムは こちら
HIRO行政行士事務所では書類申請の書き方をお伝えしたり、あるいは代行するサポートを行っています。
用途地域に関するアドバイスをさせていただいていますので、お気軽にお問い合わせください。